最近ネットニュースなどの情報で、「ミッドライフクライシス」という言葉がよく聞かれるようになりました。
これは40代・50代を迎えた人々の間で、人生の後半を見据えたときに、自己肯定感の揺らぎやアイデンティティの変化を感じ、心理的な危機に直面する現象だそうです。
この現象は、生き方や仕事、家族の役割の変化に伴い、将来への不安や身体的な衰えが原因で生じることが多いそうです。
実は思いかえせば私にも、何度もそんなことはありました。
夫とはまだ付き合っているだけの39歳の時、頚椎ヘルニアを悪化させて、手術が必要と医師に宣告された時です。
頚椎ヘルニアの手術は術後の入院が長引くため、下着やパジャマの洗濯、食事の介添がないと入院生活を送れません。
退院後また仕事に復帰できるのか、、、老後このまま一人だったら、、、と急に不安になったものです。(この時たまたま仕事で知り合った人から神の手を紹介してもらい、ギリギリで手術せずに済んだんで本当にラッキーだったんですけど。)
その後結婚して会社を辞め、すぐ台湾に移住したものの、1年3ヶ月が経った頃、激務で過労死しそうな夫に、「死ぬぐらいならいっそ仕事辞めたら?」とつい言ってしまった後のことです。
突然駐在妻から一家の大黒柱に立場が逆転したのですから、今度はこっちが死ぬんじゃないかってほど不安になりましたよ。笑
そう、ちょうど40代から50代にかけては、生活環境が変化する人が多い頃ですよね。
子育てが一旦落ち着いてきたと思ったら親の介護が始まったり、会社での中間的な立場に悩んだり、そんなこんなで家庭や仕事の責任が増えたりする中で、「このままで良いのだろうか?」といった疑問を抱く時期でもあり、これからの人生をどう進むべきか迷う時期でもあります。
そんな時にこそ、孔子の教えを参考にしてみると、自分自身を見つめ直し、前向きに未来を考える手助けになるかもしれません。
孔子の「不惑」と「知命」
孔子は中国の春秋時代に生きた思想家・哲学者であり、儒教の祖として知られています。
母一人子一人の貧しい家庭で育ち、貧しいながらも勉学に励み、やがて政治の道を志しました。実は孔子が役人として名を成したのは、50代になってからのことです。今まで積み重ねてきた実績が認められ、ようやく要職に就くことができました。
しかし他国の謀略によって国内政治が乱れると、孔子は官を辞職し、以後十余年にわたり亡命生活を送ります。
晩年は故郷に戻って私塾を開き、教育と著述に専念し、生涯で3,000人ともいわれる弟子を育て、74歳でこの世を去りました。
彼は、「四十にして惑わず」「五十にして天命を知る」という言葉を残しており、これらはミッドライフクライシスを乗り越えるための示唆に富んだ言葉として、今一度考えてみましょう。
- 40歳(不惑): 「惑わず」とは、若い頃に抱いていた不安や焦りが和らぎ、自分が本当にやりたいことや、目指すべき目標が明確になるという意味です。
- 50歳(知命): 「天命を知る」とは、人生の目的や与えられた使命を理解し、それに基づいて行動できるようになるという意味です。
- 60歳(耳順): 「耳順う」とは、他者の意見や人の言うことを素直に聞き、理解できるようになるという意味です。
- 70歳(従心): 「心の欲する所に従う」とは、心の思うままに行動しても人としての道理を外れることはなくなるという意味です。
このように、孔子は歳を重ねることをポジティブに捉え、成長と成熟のプロセスとして受け入れています。
40代・50代に差しかかることで、人生に対する不安や戸惑いを感じることはありますが、孔子の教えを通じて「まだまだ自分には成長の余地がある」と考えることができれば、前向きな気持ちで次のステージに進むことができるのではないでしょうか。
セカンドライフプランニングの重要性
WHOが発表した世界保健統計2023年版によると、日本人女性の平均寿命は84.3歳、世界第1位です。男性は81.5歳で、スイスの81.8歳に次いで2位。そして健康寿命は男女ともに日本が世界第1位です(男性72.6歳、女性75.5歳)。
健康寿命・平均寿命が延びているということは、それだけ長く人生を有意義に過ごせる可能性があるということです。
現在の日本では65歳以上を「高齢者」としていますが、先ほどからご紹介しているように、近年では一昔前の”年老いたイメージ”とは大きくかけ離れた65歳の方がたくさんいらっしゃいます。
自分も意外とまだまだイケる(笑)そう感じませんか?
孔子の時代よりも現代の方が40代や50代でも若々しい方が非常に多く、「生涯現役思考」が強い方も少なくありません。さらに、還暦や定年退職を迎えても趣味やさまざまな活動に意欲的に取り組みながらセカンドライフを楽しむアクティブなシニアも増えており、「シニア」「老後」といった言葉の価値観も変わりつつあります。
このように元気で自由に過ごせる第二の人生にするためには、40代、50代からセカンドライフプランニングを考えておくことが必要です。
「ミッドライフクライシス」を乗り越えるための3つの軸と注意点
セカンドライフプランニングというと、「貯蓄」「保険」「年金」「節税」といったマネー面ばかりがピックアップされがちです。もちろんこうした第二の人生を過ごすための”手段”も重要ですが、同様に「これから何をして過ごしたいか」と、「計画通り過ごすための資本=健康な身体」という本質的な”目的”も考えなければいけません。
ミッドライフクライシスに直面する多くの人は、自己評価や人生の意味を再考する過程で、何をすべきか迷うことが多いです。そこで、以下の3つのシンプルな軸を基に、これからの人生を再設計してみてはいかがでしょうか。
- 何をして過ごすのが好きか
自分が心から楽しめる活動や趣味を見つけ、それに没頭する時間を大切にしましょう。 - 誰と過ごしていると楽しいか
家族や友人、隣人との絆を深めることは、セカンドライフにおいて重要な要素です。信頼できる人々との時間を積極的に作りましょう。 - どこで過ごしているとリラックスできるか
自然の中や自分の好きな場所で過ごすことで、心身ともにリフレッシュできます。自分にとってリラックスできる環境を見つけ、それを活かしたライフスタイルを築きましょう。
配偶者との関係を大切に
リタイア後の第二の人生では、配偶者やパートナーと過ごす時間が増えますが、同時に夫婦関係に新たな課題が生じることもあります。
「熟年離婚」や「別居婚」、「卒婚」などという言葉が流行るように、人生の後半での関係の再構築は、避けて通れないテーマかもしれません。これを防ぐためにも、40代、50代の時から、何らかの対策を考えておく必要があります。
配偶者との共通の趣味や、共同作業、家事の分担など、お互いにコミュニケーションを大切にし、共に話し合いながら新たな目標を見つけていくことが重要です。
実はミッドライフクライシスの一番の対策は、パートナーとの相互理解です。相手の悩みや問題を共有することで、悩んでいるのは自分一人ではないと思えるはずです。
また場合によっては、周りの目を気にせず自分に正直に第二の人生をリスタートすることも必要でしょう。
自分の生きがいを見つける
ミッドライフクライシスを乗り越えるためには結局のところ、自分の「生きがい」を見つけることが何よりも大切です。
成長を意識して新しいことに挑戦する、困っている人のためになることをする、大好きな趣味を極めるといった生きがいを探し、セカンドライフを単なる「余生」ではなく、「希望に満ちた第二の人生」としてポジティブに捉えていきましょう!
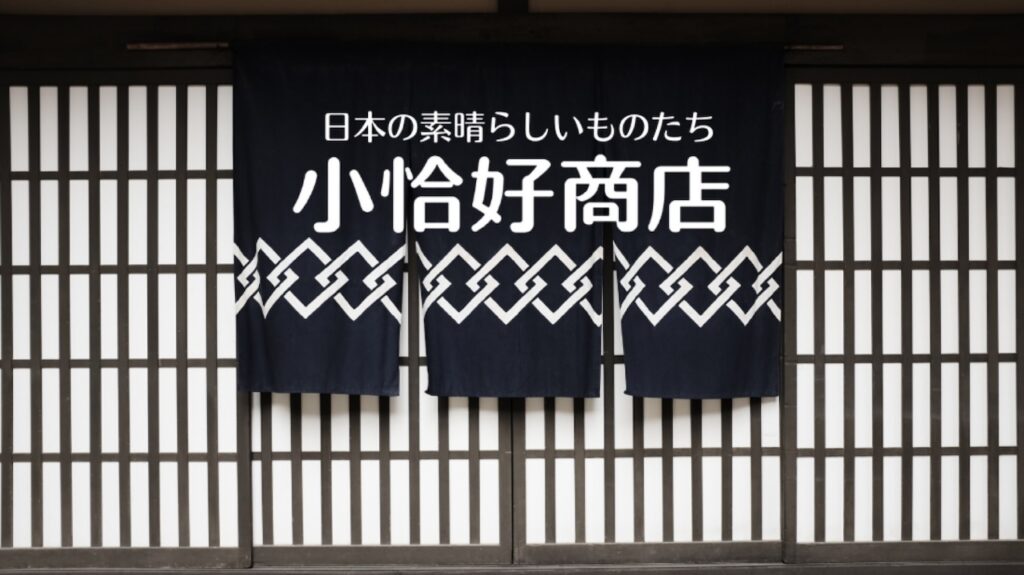
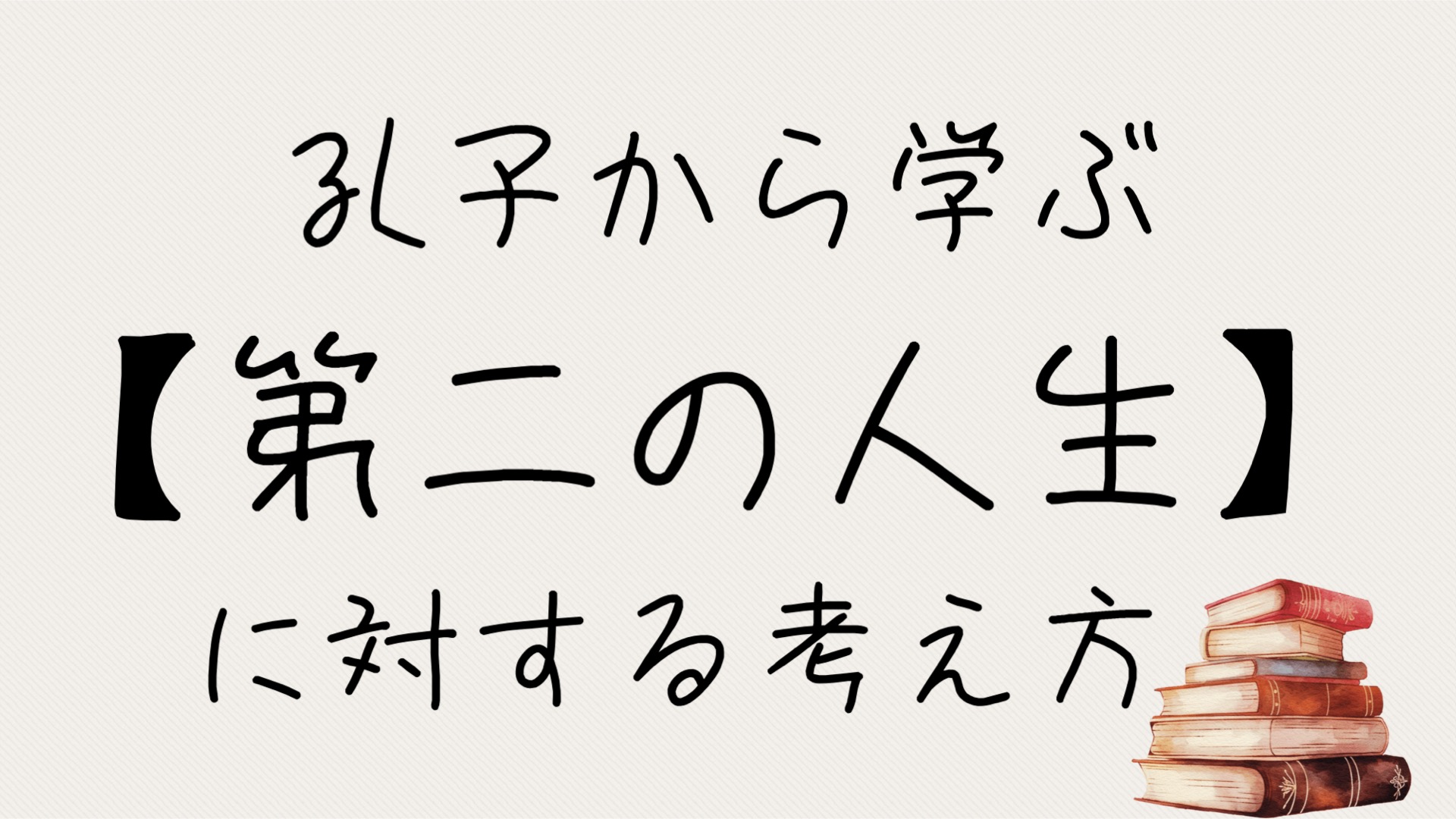
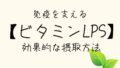
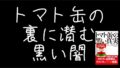
コメント