原料高と円安で、食用油が値上がりしています。
それに加えて、スペインやイタリアのオリーブ不作により、オリーブオイルがとんでもない価格になっています。また、偽物も横行し、何を信じていいか分からないような異常事態です。
そんな中、原料価格の変動の少ない日本の米油が、国内外で見直されています。
台湾食品薬物署が日本の玄米胚芽油から発がん物質検出、8トンを差し押さえと報道
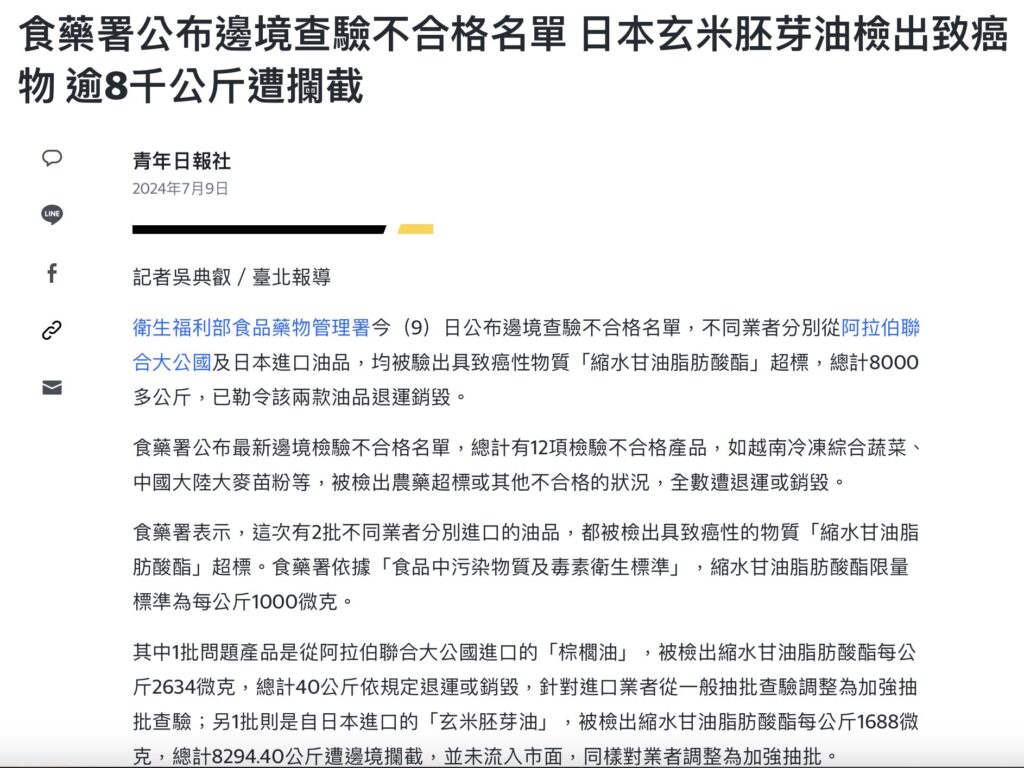
日本から台湾にもいくつかのメーカーが米油を輸出しておりますが、その中でもとてもメジャーなメーカーの米油から、発がん性のある物質が基準値を超えて見つかったということで、今年の7月に報道されました。
実際その商品を、私は「ある理由」で買ったことがないんですが、その件について、視聴者から私の見解を聞かれましたので、こちらで答えたいと思います。
まず今回問題となったのは、脱臭などのため油を高温で加熱(200℃以上)した際に発生するとされる「グリシジル脂肪酸エステル(グリシドール脂肪酸エステル)」という物質が台湾の基準値を超えていたということです。
この物質について日本では規制の対象ではなく、現在のところなんの法整備もないというお粗末な現状です。この根拠は多分ですが、国際がん研究機関(IARC)のハザード評価書で、このグリシドール脂肪酸エステルは、ヒトにおける発がん性については分類できない(Group3)とされているからだと思われます。
米油の製造方法と価格
さて、米油とは実際どんなものでしょうか?
これは、お米を丸ごと絞ったわけではなく、米の周りの糠層を集めて抽出した油のことです。
お米の構造上、栄養素のほとんどは糠層に集まっていますので、米油は栄養豊富な糠から抽出した油ということで、健康志向の方の自宅用油として年々人気が出てきました。
しかし注意しなくてはいけないのは、その抽出方法です。
米油の抽出方法には、ケミカル製法と、昔ながらの圧搾製法があります。
ケミカル製法
ケミカル製法の中には、抽出法と圧抽法があります。
抽出法とは、糠に化学溶剤を使って油を抽出する方法で、200℃以上の高温で、最終的に化学溶剤が残らないように抽出する製法です。
圧抽法は、昔ながらの圧搾製法で絞りきれなかった油分を、抽出法と同じように化学溶剤を使って抽出するものです。要するに、糠を絞った後、また化学溶剤で抽出するというカス中のカスです。笑
この溶剤抽出のメリットは低コストで製造できるため、リーズナブルな価格で商品を購入できます。
例えば今回問題となった米油も、日本の大手スーパーでは1.5リットルで862円という安さで売られています。それゆえ日本でも大変人気の商品です。
昔ながらの圧搾方法
一方の圧搾法は昔ながらの抽出法で、油本来の製法と言えます。
ただし、もっとも望ましい方法はその中でも低温圧搾法です。絞る際に熱が出ないようにゆっくり絞る製造法ですが、米油ではそのように抽出するのは難しく、おそらく米油での低温圧搾法の商品は存在しません。しかも圧搾法もとても非効率なため、新たな精製方法が生まれています。
新しい技術の蒸気精製法(スチームリファイニング法)
そこで、最近では蒸気精製法(スチームリファイニング法)という商品が出始めました。
これは、圧搾したのち蒸留・脱酸のための装置を使い、高温・真空状態でニオイや遊離脂肪酸を除去する製法となり、化学溶剤を使わないのでノンケミカルというのが売りです。
米油が体に良いか悪いかは賛否両論
「米油は体に悪い」と言われる理由は、溶剤抽出法で製造する際に、ノルマルヘキサンという溶剤を使うからです。
このノルマルヘキサンは、ガソリンに多く含まれる成分であるために危険だと言われます。
ただ実際は、抽出に使われるノルマルヘキサンは、抽出後の蒸留ですべて取り除かれるため、米油に残ることはないとメーカーは言います。ですのでその点では心配ないのかもしれませんが、今回問題になったように、ノルマルヘキサンは取り除かれたとしても、グリシジル脂肪酸エステルという物質が残ってしまうということです。
結論として、台湾ではもうこの米油は売れないと思いますが、日本国内ではまだまだメジャーな商品なため、この米油を今後も使っていいかどうか聞かれると・・・個人の判断に委ねられると思うんです。
先日も記事にしたように、食費を削っているご家庭からしたら、サラダ油は買いたくないけど、米油だったらいいよね、という見解の中で、ご家庭ごとに食費にかけられる金額というのは違うので、油の重要度をどれくらい知っていて、その油にどの程度の品質と値段のバランスをとることができるかだと思うんです。
私の個人的見解
私見的な結論でいくと、脳は65%が油でできているように、私たちの体を組成する細胞膜も油でできていますので、毎日口にする食用油も、できるだけ品質にこだわりたいと思っています。
基本的には米油より玄米で摂ったほうがホールフードで栄養バランスはさらに上です。
また、ごま油やオリーブオイルのように、ホールをそのままに低温圧搾した、化学溶剤が一切使われてない商品がベストだと思っています。
故に、この報道された米油の存在は知っていましたが、一度も買ったことがありません。
油にはもっと他に気をつけるべきところがある
今回は米油についての報道ですが、個人的には、油を選ぶ際、他にも気をつけるべきところがあると思っています。
それはなるべく原材料の生産地と製造地にも注目してほしいと思っています。
日本で製造するなら、日本の原材料が好ましいわけです。なぜなら、製造地から遠い場所の原材料を使う場合、輸送の間の劣化によるカビ毒の問題や、それを防ぐためのポストハーベスト(収穫後の農薬散布)問題に晒されるからです。
オリーブオイルと一言に言っても、イタリア製というのは嘘で、オリーブはスペインやギリシャ、モロッコ、南アフリカのものだったりするのです。ですので、製造地と原材料がきちんと表記されてない商品は避けたいところです。
たぶん知らないオリーブオイルの真実
ごま油だってそう。国産の胡麻は全体の消費量の0.1%に満たないわけです。ということは、有名な何百年と続く老舗ごま油メーカーの原材料だって、アフリカ産を使っていたりするわけです。
外国の原料の場合、日本は不思議なことに、農薬などの基準値が一気に甘くなります。ですので、老舗の国内製造だとしても、原材料がどこ産でというのがわからないければ、私は基本的に買いません。
それと、塩や醤油、味噌はなかなか腐りませんが、油は封をあけたら少しづつ酸化します。ですのでお徳用の方ではなく、なるべく小さいボトルサイズの、遮光性の高いガラス瓶に入ったものを選び、新鮮なうちに使い切れるものを買います。よく頻繁に使うのでしたら、お徳用サイズを選んでもいいですが、必ず遮光性の高いステンレスオイルサーバーに移し替えてこまめに詰め替えることをおすすめします。なるべくフレッシュな状態で使えるように気をつけましょう。
私のように口うるさい人は、それなりにお金がかかってしまうことを覚悟しての購買行動を日々しています。だから、一概に私のようにこだわりなさいと強制することはしません。それぞれのご家庭の家計に照らし合わせて、場面場面で判断する他はないと思います。
今回の問題について
今回問題となった「グリシジル脂肪酸エステル(グリシドール脂肪酸エステル)」という物質ですが、国が変われば基準も大きく変わります。
ですので一番の防御策は、常日頃から食品製造における化学物質の使用に敏感であれば、このような懸念のある商品を最初から選ばないということです。
このような商品があることで、安価に米油が手に入るという良さはあっても、果たして自分はそれを受け入れるのかどうか、、という個人的な判断に委ねられますので、一概に良い悪いとは決められません。
圧搾式は手間暇がかかる上、大量に生産することもできません。ですので価格が高い。これは仕方がないことですし、それでもこだわって生産している人々を私はいつも応援したいと思っています。
今回のような問題をキッカケに、そういう小さなメーカーさんの仕事やこだわりに対する理解や、価格に対する認識が変われば良いなと思っています。
ですので、より多くの方が、このように生活に溶け込んだ化学物質について、もっと敏感にYES、NOを消費者として突きつける必要があります。
いつも言ってますが、「お金は投票権である。応援したい企業の商品を購入し、世の中ではメジャーだけれど、自分は受け入れ難い商品にはお金は使わない。」そういった賢い消費者で常にありたいものです。
今後ともよろしくお願いします。
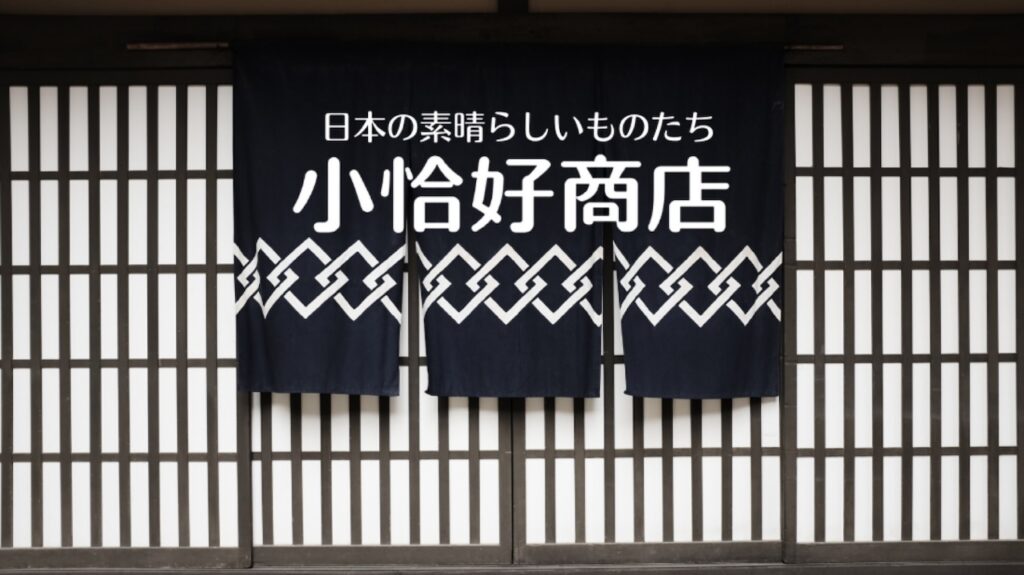
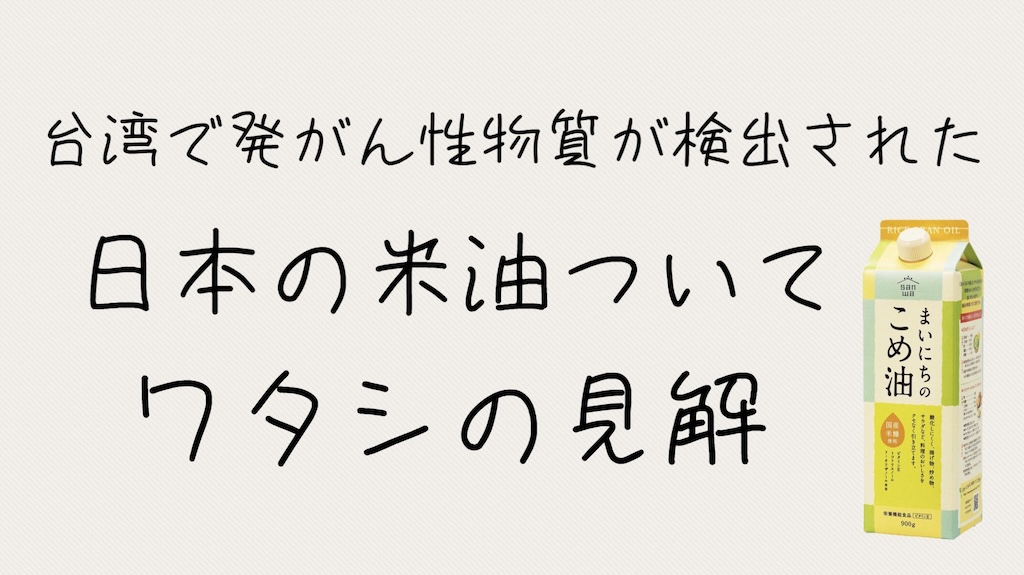
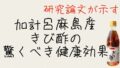

コメント